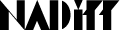丹羽良徳|藤田直哉|丸山美佳|F.アツミ
NADiff a/p/a/r/tに於いて、アーティスト・丹羽良徳の作品の批評集『資本主義が終わるまで』の刊行を記念したトークイベント「芸術祭の公共圏 ―敵対と居心地の悪さは超えられるか?」を2017年に開催しました。当日、丹羽良徳、藤⽥直哉、丸⼭美佳、F.アツミ、4名の出演者により行われた対話のドキュメントを一部掲載します。
2017年11月開催「芸術祭の公共圏―敵対と居心地の悪さは超えられるか?」
>>開催概要(終了)
アツミ:丸山さんは本書『資本主義が終わるまで』に、「ウィーンの勝利とルーマニア―グローバル資本主義に消される歴史」というタイトルで寄稿してくださいました。
丸山:はい、どうも。ウィーンから参加しています、丸山美佳と申します。今回、丹羽さんの本には、2015年に始まったウィーン・ビエンナーレの展覧会を中心にしたテクストを寄稿しています。第1回目のビエンナーレの主要展覧会の一つがルーマニアについてであったことと、丹羽さんの作品には共産主義のシリーズがあって、その最初の場所がルーマニアであったという関係で書きました。
たぶん丹羽さんが活動場所にウィーンを選んだ一つの理由でもあると思いますが、ウィーンは文化的にも地政学的にも東ヨーロッパと西ヨーロッパをつなぐ境目であり、窓口のような場所なんです。ウィーンは東ヨーロッパと西ヨーロッパ両方をつなぐ街としてアートを押し出す政策をしている場所の一つでもありますが、その一環でビエンナーレではルーマニアを意識した展覧会になったのではないかと思います。ルーマニアに代表されるような旧東側の共産主義は、西ヨーロッパではいわゆる悪いものであったり失敗したものであったりして、丹羽さんの作品でも垣間見られますが、東ヨーロッパにおいても負の歴史として残ってしまっているものです。その失敗として理解されている共産主義の歴史があるなかで、ルーマニアは西ヨーロッパ的モダニズムを考えるうえで重要な場所であったにもかかわらず、共産主義によってそれが断絶してしまったという背景を押し出すのが展覧会のストラテジーだったように思います。その共産主義にだめにされてしまったルーマニアをもう一度西ヨーロッパのアートの文脈へ呼び戻そうという意図があって、共産主義の歴史を断罪して風化させることによって、西ヨーロッパのいわゆる人文主義的なところを打ち出そうといったところがありました。
特にウィーン・ビエンナーレは都市型とはいえ、ある種の「地域アート」なんですけれども、西ヨーロッパ側であることが強調されています。日本の「地域アート」のようなものとは少し違って、地理的な歴史や、主催者側の政治的関係が垣間見えていました。町とかそのデザインとか資本の動きとか、そういうものすべてを含めてビエンナーレが構成されていて、西ヨーロッパとして、世界に対してウィーンをどう見せたいのかということを見せる機会になっていたという感じがしました。
藤田:日本の「地域アート」と違って、ウィーンでは共産主義とか、社会主義とか、新自由主義とか、民主主義とか、そういう問題がむしろ出てきやすい地政学的な条件にあるんですね。それ自体を「戦略」として選ぶ巧みさと必然性もあるわけですね。政治的なテーマと、地域のブランディングが重なる。
丹羽:ウィーン・ビエンナーレは地政学的な条件から、かつて共産主義体制であったルーマニアをウィーンが見せてやるぞというような上から目線でやっている部分が非常に目立つのはいかがなものかという内容だったと思うんです。帝国主義時代、冷戦時代の歴史的な力関係の延長上に生きているわけだし、いまだに東西の経済格差も大きいし、ウィーンでビエンナーレが始まったときにルーマニアを見せようとすると、そういう傾向になってしまうのは避けられない。やっぱり、観客側もウィーンは西側諸国の都市として旧東側を見せたいんじゃないかという感想が出て当然かと。
アツミ:丸山さんの批評では、ビエンナーレが“勝者”の論理によって地域の歴史を書き換えていくことに対する批判的な眼差しも見られますが、それは芸術祭が行政や運営側の論理によって公共圏が提示されることに対する危険性を示唆しているようにも読めます。この批評のなかでは、丹羽さんの「ルーマニアで社会主義者を胴上げする」(2010年)という作品にも言及していて、ルーマニアの若者と社会主義者のかみ合わない会話から、ルーマニア革命の後で共産主義の歴史が否定され、資本主義の現実に飲み込まれていく暴力的な空虚さについても書かれています。この作品も観客の共感や認識の仕方によって、社会主義者を一方的に攻撃していると見る人やイデオロギーの時代的な変容を見る人など、その解釈と受容にはさまざまなバリエーションが見られそうです。
ところで、丹羽さんは、共産主義者やイタコ、あるいは台湾のストリートの人など、公共空間に生きる人々からさまざまな声や語り、あるいはナラティブを集めて、編集して、作品をつくっていくというスタイルがあると思います。まずうかがいたいのは、どうしてそんなにたくさんの人のナラティブを執拗に集めるのでしょうか。作品のなかでは、その人々の態度やナラティブが編集されることによって、ユーモラスに立ち現れたり、あるいはアイロニーを感じさせるものになったりしていると思います。丹羽さんの作品に批判的な態度をとる人は、丹羽さんのその取材や編集へのスタンスにどこか独我論的な暴力性を見いだしているようにも思えるのですが。
丹羽:一つは作品制作の欲望のなかに、いつもどこかにジャーナリスティックな視点があるんです。今生きている社会の構造にいかなる力が働いてこのような結果が生まれているのかというのを解明したいという欲望がまず一つある。ジャーナリズムでいうところの「取材」にあたる作業ですが、インタビューをとりに行くという作業は、例えば社会学者の人だとか、本を書く人だとかがとる方法の一つですね。僕は作品じゃないところで、情報を集める段階でそういったことはもちろん重要だからやっているんですけれども、作品をつくろうと思ったときに、普通のインタビューだけでは物足りないときがあるんです。インタビューをしますって言って答えてっていうことでは、たいしたことは答えられないんじゃないか。あるいは、答えてもらえない。何か視点を変えた方法でインタビューをするか、場合によってはある種のプレッシャーを与えないと答えられないものもあったり、その対象が嫌かもしれないけれども少しきわどいような方法をもってしないとわからないもの、本人にも理解してないものを掬い上げるために、僕はその方法をとっています。それがアツミさんが言うナラティブを集めている理由なんですけれども。端的にいえば、ドキュメンタリーに近いともいえる。
藤田:社会の構造と力を解明したい、という点は面白いですね。もし可能なら、芸術祭の公共性と、その方法との関係についても、うかがえたらうれしいんですが。
アツミ:社会の構造と力ですか。そういうところから考えると、いつだったかジュリア・クリステヴァはフェノ・テクストとジェノ・テクストという概念を用いて記号分析学を展開していましたよね。そのうえで言うと、一つの正史といわれるテクスト(フェノ・テクスト)が無数の偽史として排除されたより深層のテクスト(ジェノ・テクスト)を生み出す声や身振り、そして書かれえたものを現在にあらためて出現させているのが、町長や共産主義の作品であるといえるかなと思いました。
つまり、丹羽さんの作品には、人々のナラティブを時空間を超えて集めることで、大文字の歴史を構成する出来事や物語に対する正統な解釈から排除された解釈をもう一度拾い上げていく一面を見ることもできると思うんです。社会の構造がある一つの正史のうえに成立し、人々がそのなかで善/悪の規範に則ってコミュニケーションをとっているのであれば、その正史や規範を揺るがすような異議申し立てを作品のなかの人たちのナラティブに見ることもできるのではないかと。その人々の歴史への異議申し立てが、権力のスタティックな均衡にダイナミックな変容をもたらす力となって観客へと感染するといえるのかもしれません。そして、それは人によっては薬にも毒にもなる。つまり、賞賛されたり、拒絶されたりする。あるいは、ある正統とされている解釈に対して異端とされ見向きもされないような解釈が衝突するときに、藤田さんが話していたようなざらざらした感じが出てきて、公共と人々との間にあるギャップを見直す契機が起こり、公共空間における違和感と和解する可能性が生まれるのかなと思うんです。丹羽さんの時空間を超えた人々との対話、あるいは歴史に対する異議申し立ての折衝という制作への態度は、芸術祭の公共圏を考えるときに一つの契機となるような気がします。
藤田:今回のトークイベントのテーマにもある芸術祭と公共性ということを意識して話すと、その観点から丹羽さんの作品を考えるときに、今の話は大変興味深いです。丹羽さんの作品というのは捉えどころがない部分があって。確かに映像としては面白いんですよ。ユーモラスだし、僕らが想像したり、見たりしたことのない細部がある。例えば、共産主義者を胴上げする作品では、現地に行って日本人が人を組織したり、共産党の支部に入ったりしますが、最終的にはみんながわあわあ面白がりながら胴上げをしちゃう。身体的なレベルで、すごいっていうのは感じる。ただ、それが具体的に社会にどう動かして、どういう効果があって、公共性とどういうつながりをもっているのかということについては、意外と見えにくい。言語化しにくいと言い換えてもいいかもしれない。むしろ、言語化しにくい身体レベルや情動レベルでのニュアンスを捉えていることが、丹羽作品の意義なり、批評性かもしれない。けっこういくつか作品を見ているんですが、作品の位置付けがまだよくわからないんですよ。
丹羽:芸術祭と公共性というトピックスで僕の話ばかりしていると、よくわかんなくなってくるんだけれども。僕はアーティストなので作品のモチベーションを話すことしかできないし。例えば、僕がルーマニアもしくは日本でつくっていた共産主義シリーズだと、僕は1982年生まれで、共産主義がかつてあったであろうというところに対して、僕はその日本で経験しえない、よくわからないものに、2010年代から遡行して現代の価値観から応答していくということが、僕の作品単体でのモチベーションになっている。芸術祭の公共圏と今どうこの流れがつながるのかっていうのが言えないんで、ちょっとアツミさんに戻してもらいたんですけども。
アツミ:「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらう」という作品に戻ると、これは「直島町史」というある特定の為政者によって編纂された歴史に対する、別の為政者、そしてそれを選んだ人々の異議申し立てをイタコといった遊民のような存在に代弁させているとも見ることもできます。つまり、直島という公共空間に対して、時代を超えた別の公共空間のあり方や権力関係のダイナミズムを提示することで、複数の公共のイメージの集まりという意味での公共圏について考えさせてくれると思うんです。
瀬戸内国際芸術祭2016についていえば、丹羽さんの作品をはじめとして、その他にもさまざまなモダニズムの困難さを批判的に考えさせる作品がありましたが、それによって芸術祭がファッションとして受容されるだけでなくて、地域の歴史や権力構造などについても観客の思考を促す複数の公共のイメージを、つまりは公共圏を提示することができていたのではないかなって、言えると思うんですが。
藤田:以前、田中功起さんと杉田敦さんとここで「共同体と現代アート」というテーマで話したときにも、共同体の定義がいくつもあるよねといった話をしたんですよ。公共性のバージョンの話になるのですけれど、「公共」が何を意味するのかも複雑で、国家とか自治体という意味もあるし、政府や公権力とは離れたところでのパブリックな人々の民衆の集まりということもあるし、いろんな公共観ってあるんですよ。
「公共」のイメージも地域や国ごとで全然違うと思うんだけれども、丹羽さんの作品の場合は「公共」のイメージ自体を独自に変えようとしている感じがして。丹羽さんという現代の日本に生きている1982年生まれの人が、いきなり旧社会主義圏に短絡して変な文脈を無理やり重ねている。突発的な事故のような線のつながり方を行って、存在していなかった共同性をつくりだして、公共かどうかよくわからないものが瞬発的に生み出されていると思うんですよ。それが現実をどう変えるか、公共性とどういう関係になるかはわからないけど。変なふうにずらしながら、つながらないものを無理につなげている。現在ある「公共」とは違うプラットフォームをつくってみる、という実験にも見えます。だからコラージュとかダジャレみたいに、ユーモアが生まれるんですよ。つながっちゃいけないものからつながっているギャップの面白さってあるじゃないですか。同時につなげちゃいけないものをつなげるから、炎上するんですよね。
丹羽:なるほど。
アツミ:炎上に引きつけて言うと、丹羽さんは出演者との交渉や撮影中の自演、あるいは編集作業のなかで、敵対、あるいは不和や対立を露呈させることをいつも意識しているのでしょうか? 出演者の態度にユーモアを感じる一方で、その制作上の操作についてはどこかアイロニカルな態度も感じられます。いろいろな人に出会うときには物事を知らないで、あるいは知らないふりをして話しているけれど、事後的にはすべてを知ったうえで編集して作品にしていますよね。
丹羽:明らかに対立を生むようなことや、何か知らないふりをしてお願いすることはやってないです。まったく違う立場の人たちを強制的に同時に一つの場につなぎ合わせるとか、自由意志に反して無理に会わせるっていうことは、僕の作品のなかでは出てこない要素だと思っている。とはいえ、今までつながらなかったものを視点を変えてつなげるっていうことは行っています。その結果として、予期せぬ敵対が生まれるっていうことはあるかもしれない。例えば、直島の作品で町長さんに「過去の町長さんが霊体で表敬訪問に来るので対応をお願いします」ってお願いしたとして、確かに町長さんは困ったもんだなと感じたと思いますよ。ただ、それによって町長さんのなかに未知の存在に応答するある種の緊張感が出てくるのは僕の作品にはあるとは思う。
アツミ:丹羽さんと出演者の間で交わされる対話から生まれる緊張感であったり、さらには映像作品として編集するときのその緊張感の操作というものについては、観察の水準を上げていくといろいろと考えられそうですね。歴史や政治をめぐる緊張感について考えられるかどうかも、芸術祭について評価するときの一つの視点になるかもしれません。
アツミ:というのも、先日、ドクメンタ14を見るためにアテネに行ってきたのですが、主にヨーロッパが抱える政治や歴史の問題を扱う作品やパフォーマンスがたくさん見られました。シンタグマ広場ではトルコでのクルド系の衛星チャネル廃止への動きに対する数人のダンスデモがありましたが、アート作品なのかどうかすぐにはわからなかったくらいです。日本の「地域アート」でも、地域の公共性を支える政治や歴史、あるいは公共圏のイメージに意識的なプログラムや作品群が充実していく可能性はあるのでしょうか。丸山さんは、今回のドクメンタ14をどのように見られましたか?
丸山:「地域アート」や「公共」に関して言うと、ドクメンタ14の内容もそうでしたが、ドクメンタ14自体に対する批判的なアクティビティが何個かあったのが印象的でした。その一つで気になったのは、ロジャー・バーナットに対する「Lgbtqi+Refugees」というギリシャのグループの反応です。バーナットの作品は古代ギリシャの宣誓の石のレプリカをいろんな人たちに渡してパフォーマンスをしてもらうというものでしたが、そのパフォーマンスに参加したこのグループが、作品がLGBTQIといった性的マイノリティや難民をエキゾチックな「他者」としてフェティッシュ化しているということで、その石を盗んでウェブサイトにステートメントを発表したんです[1]。それはウィーンでも話題になっていました。作家はこのステートメントに対してグループを批判をしていますが、彼の言い分としては、グループに支払いはしていたというものでしたが、この批判的なパフォーマンスのおかげで作品が注目を浴びて、最終的に意図していたことはできなかったけれど、結果として作品がうまくいったということも言っていました。
ドクメンタ14は確かにマイノリティの声を拾っていくということを重要視していたわけですが、結局、問題になっていたのはアテネで実際に「マイノリティ」として扱われている人たちにとっては、それがアートに利用されているようにしか思えなかったし、そういう批判があったときに、作家との対話があまりうまくいってない部分があったという印象でした。大きな芸術祭には歴史的に見ても批判がつきものですが、ある地域性の問題を扱っていたりする場合は、その当事者の声を拾いはするけれど、本人が実際に登場してくることに関しては受け入れることができないというアート側の問題がドクメンタ14にも出てきていたと感じました。
アツミ:公共空間で現実的にマイノリティとして抑圧されていると感じている人たちが、アートのマテリアルとして集められて、フィクションとして消費されてしまうという問題を思い起こさせてくれますね。あるいは、アートが「マイノリティ」の声を一方的に搾取しているだけで、対話が醸成されないという状況もあるのでしょう。ただ、観客がアート作品やそれに対するアクティヴィストの応答についてインターネット上のニュース記事を見ていろいろと考えたり、そこから公共空間のなかでさまざまなレイヤーで対話が生まれるということもあるでしょうね。
その一方で、アーティストが作品をつくるなかで、参加者や観客が不快になったり、傷ついてしまったりするという、表現の自由が人々に対して暴力として映ってしまうという問題もあります。マイノリティの声を拾っていく、抑圧されている現実を暴くといったときに、観客や専門家はどのように制作プロセスや制作物を評価するのかということも必要な議論でしょう。ただ、いずれにせよ、アート作品とアクティヴィズムが出遭い、観客がさまざまな対話を行うという意味では、芸術祭は人々が対話するための公共的なプラットフォームとして機能しているともいえるのではないでしょうか。
藤田:アツミさんがおっしゃっているのは、芸術なり言説なりが、闘技的、闘いや議論であり、とりあえずたくさん出て議論できるテーブルこそが公共性だっていうご意見ですよね。
アツミ:そうです、理念的には。
藤田:たぶん、疑問に付されているのは、そういう討議空間としての公共性なんじゃないかと思うんですよ。少なくとも、出版なりカフェなりを物質的な基盤として考えられてきた「公共圏」の考え方は更新しないと使えない。例えば、今話に出たインターネット上の炎上とかは、それぞれのいろんな人の意見がわあわあ出てくるけど、討議なり闘技として期待されている有益なものを生んでいるのか。ただリンチになって、たいして思考も発展しないで終わる。こういう状況を見ていると、たぶん旧来のモデルではなかなか難しいのかなって思うんですよ。少なくとも、討議的理性が万人にあるとか、言説の自由市場とかは、もう前提にできない。だからヨーロッパではネットを法規制したり、アメリカではテクノロジーで押さえ込もうとしているんだと思うけど。
僕の考えでは、アートが公共性の問題に取り組むのは、この問題系にネットや法や技術とは異なるアプローチをする必要があるからだと思っているんですよ。芸術祭とか、あるいは丹羽さんみたいに人を集めて何かする作品っていうのは、そういうこれまで考えられてきた公共性、公共圏のモデルでは成立しえないような公共性、公共圏の条件の考え方を再発明する営みだと考えたほうが生産的だと思うんですよ。例えば、「地域アート」や芸術祭も、利害関係がそれぞれめちゃくちゃじゃないですか。政治的な利害があり、行政がいて、芸術家もいて、ただの観光客もいて、そんな感じでものを考えて、違う人が来て、重なって、ちょっとでも触れ合っていくっていうことの意義ってあると思うんですよね。たぶん、そこで生まれているのは、ハーバーマス的な公共圏ではない。じゃあなんなんだろう。たぶん、まだ概念ができていない。
アツミ:先ほどの公共圏のイメージと異議申し立てということに戻ると、異議申し立てには敵対(アンタゴニズム)と闘技(アゴニズム)という2つのイメージがあると思うんです。一つはクレア・ビショップが美学的な考察[2]のなかで発展させた敵対(アンタゴニズム)であり、もう一つはシャンタル・ムフとエルネスト・ラクラウが政治思想史のなかで展開させた闘技(アゴニズム)[3]であるとして考えてみましょう。そのうえで公共圏における対話のあり方について考えると、ネットの炎上はどちらかというとマスメディアやアクティヴィズムが構成する傾向にあるステレオタイプな善/悪に分かれて、闘技(アゴニズム)としての対話が見られるような気がします。それに対して、丹羽さんの作品を敷衍してみれば、アートを起点とする敵対(アンタゴニズム)としての対話では、スタティックな二項対立に対して第三項としての別の仕方での態度や言説を表明する契機を見いだすことができると思うんです。そして、今日のテーマに引きつけて言うと、それを「敵対の公共圏」と呼べるかもしれない。どこか「居心地の悪さ」を感じさせる公共圏のイメージだけれども。
そういえば、丹羽さんが「House of Day, House of Night(昼の家、夜の家)」の「真のアカデミー(講義・演習)」で行った「88の提案に向けて」(2016年、@KCUA)というワークショップを実施したときも、TwitterをはじめとするSNS上では炎上が起こっていましたね。『社会の芸術/芸術という社会』[4]の本のなかでは、「デリヘルアート事件」という表現で批判的に言及されていましたね。
藤田:みなさんはご存じですか?
アツミ:今日ここにいる30人くらいの方々のうち、丹羽さんの「88の提案」から起こった炎上のことを知っているのはどのくらいいますか? もしかして、手を上げてもらっても大丈夫でしょうか。なるほど、けっこう・・・。
丹羽:全員、知っています。
アツミ:いや、全員っていうことはなかったよね(笑)。『社会の芸術/芸術という社会』では、丹羽さんの「88の提案の実現に向けて」というワークショップに端を発するSNS上での炎上について、「デリヘルアート事件」という印象的な表現を用いて通奏低音のように各所で言及されています。筆者や編者のこの件についての解釈やその背景にある経緯や意図をうまく把握できないので話しにくいのですが、当日のイベントをビデオ撮影していた人として言っておいたほうがいいことは、ワークショップ当日の最初から最後まで、感覚的な面白さを理由にデリバリーヘルスに従事する当事者の人を呼ぼうとした人は誰もいなかったということなんです。
京都市立芸術大学の大学関係者から聞いたのですが、この見解は大学内で当日の録音・録画資料を検証したうえで共有されている認識でもあります。丹羽さんのワークショップに関するインターネット上で公開されている記事や『社会の芸術/芸術という社会』の記述内容については事実誤認を指摘できるとして、関係者はとても困惑し、憂慮していました。関係者によれば、@KCUAはワークショップでは人権の侵害がなかったとして公式見解をとくにあらためて発表していないそうです。当日の状況について関心のある人は、『フレーミングするパレルゴンのパルマコン―丹羽良徳の〈88の提案〉を後に』[5]という批評を公開しているので、よかったら見てみてください。
藤田:これは「デリヘルアート事件」に対する、公の場での初めての応答と認識していいですか?
アツミ:そういうことになるのかな、どうだろう。何をもって公というかがわからないので難しいところ。批評はすでにインターネット上で公開しているし。そのことを認識している人は、すでにビデオを撮っていた人にとっての当日の状況認識や解釈を認識していると思うんです。あと、学芸員の人たちは個別に事情を説明して、ワークショップの企図について理解を得ているとも聞いています。現実にたくさんの人たちの前で声にして発言するということを公での応答というのであれば、ぼくにとっては初めてといってもいいのかもしれません。
でも、見方を変えると、炎上があった翌月くらいに丹羽さんは公開のトークイベントをしていたので、初めての応答ということでもないと思います。このトークイベントの内容は当初ドキュメントとして公開されるはずだったのですが、諸事情で未公開のままのようなので、知らない人も多いかもしれませんが。それよりも、この件について読み解いていくと、もう少し大切なことがあります。
藤田:つまり、見た人の観察者の1人としての主張が採用されて炎上したと。真面目にいえば、対面コミュニケーションと、インターネットでのコミュニケーションの2種類がつながったときに、断層やズレのようなものが生じたということですよね。
アツミ:そうですね、たしかに。町長の作品の話でも出たように、参加型の作品になると誰もがすべてを見通すことは不可能に近いんですよね。そういった状況のなかでどの部分を切り取って、事実って言ったり、あるいは事実誤認って言ったりするのか。それは難しい問題だと思います。ただ、そのような認識と誤認をめぐる解釈論争によって、現実の見え方が多様になったり、そこからステレオタイプな二項対立ではない別の仕方で議論をすることを可能にしてくれるのも、アートのもつ力というか、敵対の効果かもしれませんね。それが「真の(いきいきとした)アカデミー」というワークショップだったと解釈できるのだろうか。あのワークショップとその後日談は結果として、歴史的、政治的な問題を扱うコンテンポラリー・アートの受容をめぐるさまざまな解釈のコンフリクトやそれに対する観客や関係者の態度について考える契機になったと思う。
ただ、藤田さんも先ほど言っていたように、ネット上で炎上が起こってしまったときに別の意見を発話することはとても難しくなってしまう。そして、いつの間にか一面的でステレオタイプな主張が、あるいは頑強なイデオローグに支えられた見方が、その他の意見や見方を事実上、抑圧してしまっていたという流れができてしまう。その結果として、さまざまな立場にある人の声に十分に耳を傾けず、現場で起こったことから切り離された事実誤認ともいえる解釈や、一方的に他者を批判する見解やそれを支える認識に基づいて、例えば「HAPS PRESS」[6]では表現と倫理をめぐる対話のドキュメントが公開され、「京都新聞」[7]での文化欄に掲載され、そして『社会の芸術/芸術という社会』という書籍が出版されてしまう。確かに多様な思想信条をもって対話するという態度を理念的には護持する必要があると思うけれど、仮想現実が現実を圧倒してしまって、議論が事実から解離して展開していくという実際的な課題もある。そこには現実仮想というか、出来事と虚構性をめぐる本質的な問題が隠されているかもしれない。そのようななかで、参加型アートやワークショップへの参加者、あるいは観客は、どのように対話から公共圏のイメージを豊かにすることができるのだろう。
丹羽:僕からいえることは、さまざまなレベルでの対話をあきらめないこと。一般には対話が見えないかもしれないけれど、僕がやってる対話が一般に出ていないじゃないかって言われても、ネットに何も書いていないじゃないかって言われても、ネット上に出していない情報も含めて、僕ができる対話を実際にやっていこうと思っていて。それにはすごい時間がかかろうが、何年かかろうが、僕は死ぬまでやるのかもしれないけれど、今ここですぐに暫定的な答えを出してこうでしたっていうふうにはやらない。僕はとにかくいろいろな人たちと話を続けてその都度考えを更新していくっていうのが、僕なりの今のところの応答です。
例えば、その直接来てもらったげいまきまきさんとどんな機会でもいいからご飯を食べに行く、それで体感的に、経験的にわかることもあるかもしれない。はっきりしているのは、企画者であった僕の対応が雑だったっていうのは認めているし、それはもう僕は反省しなきゃいけない。ただその先は、制作を別のかたちで続けていくとかっていう、例えばコラボレーションのようなものにしていくとかも含めて、すごい広い視点で何らかの応答をあきらめないで続けていくことかな。
一方、炎上それ自体でいえば、炎上が起こることで他人の言説と自分の欲望が同化されて、さらにはそれがあたかも真実であるかのようなストーリーが形成されますよね。ちょうどそういうことを考えていたときに、「2020年の東京オリンピックで日本人選手がボイコットしたら?」という未来形のフェイクドキュメンタリーのアイデアが浮かんだんです。
藤田:今、実は炎上とデマというテーマについての本をつくっているんですけど。
丹羽:おお、面白い。
藤田:その観点からいろいろと言いたい部分もあるんです。『ネット炎上の研究』[8]という研究書があるんですが、著者の山口さんが問題視しているのは、炎上が言論を萎縮させることなんですよ。今回のケースも、まあ公に言われていないかもしれないけれども、現状を忖度して声明が出せなくなったり、議論できなくなったり、反論できなくなった部分がいっぱいあるじゃないですか。炎上っていうのは、公共的なテーブルそのものを破壊する行為だなと感じます。しかし一方で、それはインターネットやSNSという新しい「出版公共圏」に変わるプラットフォームによって成立しているものでもあり。
これまで、炎上するアーティストっていっぱい見てきていて、カオス*ラウンジであったりブラックボックス問題だったり、こう現象はなぜ起きるのかっていうことも考えるのです。丹羽さんは、社会にコミットして、そこで動いているルールそのものをちょっと介入させて、可視化させたりね、違和感なりを生むことを重要視している作家ですよね。そして、ある時期以降の芸術は「異化効果」っていうのかな、社会とか人に違和感を与えたりしての認識を変えるところをいいと考える芸術観がありますよね。丹羽さんを含むさまざまな作家は、社会や権力なり、人間がかかわるダイナミズムに介入しながら、異化効果を生み、それが芸術的効果も、政治的効果も生むんだと思う。で、倫理とか、社会とか、システムとか、ルールをいじるタイプの作品は、もう存在の条件として、反発を生むから、炎上が起きるのはまず最初の理由にある。
でも、一方で重要なのは、SNSなどのメディアそれ自体が、異なった価値観の人どうしを短絡してつないじゃうってところがある。それが多様性につながる期待もあったけれど、「炎上」という現象は一面的な価値観を支配的にしかねない圧力としても機能しているよね。その「居心地の悪さ」に反発する人もいる。丹羽さんの場合は、作家性からして必然的な部分もあるっていうか、この問題から逃れちゃいけない。丹羽さんって日本の80年代生まれ的な人が、社会主義とか、共産主義のところに、飛行機でぽんと金出して行っちゃって、短絡させることがユーモアと作家性の価値を生んでいるんだから。そのなんて言うか、その異なるコンテクストのものをぶつけることの面白さでやってきた人だからこそ、異なるコンテクストがぶつかることによって生じる誤解や喧嘩みたいな炎上の現象を必然的に招くんですよ。だから、兄弟みたいなものなんですよ、炎上っていうのは(笑)。だから、そこを組み替えるようなことをアートとして取り組まなきゃだめだと思うんです。
丹羽:藤田さんが今言った乗り越えるべき方法が、僕が取り組むべき重要な課題かつ必要な作業ですね。
藤田:言い換えると、炎上の問題には日本の公共性の問題点が凝縮してるんですよ。それはルールとかさ、人はこうあるべきだっていう規範の意識があって、それがずらされたときに生じているわけだから。作家は、必然的に現れるそれを、受け止める必要がある。もちろん、精神的にしんどいし嫌なのはわかるけど、そういう個人的な事情を超えることが「公共性」が揺らいでいる時代と格闘して新しい提案をするためには必要だと思う。
丹羽:そうですね。つまり、僕はいつか起きるだろうとうすうす思っていて、いつ起きるのかはわからないけれども、どこかで起きて当然だろうって。僕なりに冷静に考えると、藤田さんの言っているとおり必然だと思います。これから僕が作家としてこの現象をどう生かしていくのか、それをどういう方法で応答していくのかっていうことは深く受け止めるべきだと思う。今日のテーマである「芸術祭の公共圏」というところで言うと、僕以外の作家でもこういうことを起きる人はたぶんいると思うんですよ。それを全体の芸術祭としてどういうふうに考えていくのか、そして芸術祭をどう設計していくかっていうところで意見を聞けたらなと思います。
藤田:その手前の話でうかがってみたいことがあって。炎上は日本では頻繁に起きて、それで言論なり表現は萎縮しているけれども、ヨーロッパの作家の場合は炎上したりないんでしょうか?
丹羽:日本のSNSのような燃えるプラットフォームがないけれど、実際の議論は多いにあると思います。丸山さんがどう思うかは知らないけれども。
藤田:炎上と議論の質的な差異もあるかもしれませんが。
丹羽:丸山さん、お願いします。
丸山:私が知っている範囲ですが、ツイッターとかそういうレベルで議論が盛り上がって炎上することはあまり聞きません。批判の声明を出したり、あるいはそれに応答したりすることで、その後のディスカッションが活発化するっていうのはあると思います。それらの動きに対してジャーナリズムが働いて、ニュース記事にもなることが多いのではないでしょうか。さっきの「Lgbtqi+ Refugees」の場合は、彼らが声明をインターネット上に公開した後にSNS上で広まっていました。もう一つドクメンタ14のケースで言うと、ホロコーストをモチーフにしつつ、ギリシャの難民問題を扱ったパフォーマンスへの批判が多くてキャンセルしたケースもありましたよね。ドクメンタ14はその対応について声明を出していましたし、キャンセルされた作品の代わりに詩の朗読と議論の場を設けたりしていました。個人的なものであれ、公的機関によってであれ、パブリックな情報に対してリアクションをするのは、展覧会レビューを含めてよく目にした気がします。炎上というよりは、自分たちがどういう状態にいるのか、問題の原因や経緯、あるいはこういうことを考えているといったことを発表することによって、問題を炎上にとどめるのではなく、その後の議論の助けになっているのではないかなとは思います。
藤田:ということは、じゃあ何か芸術家が挑発的なアクションをしたら、それに対する議論が起こって、パブリックな状態でパブリッシュして、議論が蓄積して、歴史が進んでいくわけですね。日本ではどちらかというと、炎上したらすべて隠蔽されて終わりみたいになりがちです。
丹羽:そうですね。僕が知ってる例だと、歴史的な背景からユダヤ人権団体の抗議が東ヨーロッパのほうでは多いと思うんだけれども。クラコフ現代美術館の展覧会でアルトゥル・ジミェフスキがアウシュビッツから生還したユダヤ人に当時収容所で使われていた個人認識番号を示すタトゥーを入れ直すという映像作品を展示しようとしたんです。時間経過とともにタトゥーがどんどん消えていくんだけど、彼らの壮絶な記憶は消えることがない。しかし、アルトゥルはそのタトゥーを入れ直すっていう暴力的なビデオをつくり展示したときに当然抗議を受けて、その結果、実際に作品が中止になった。ただその続きがあって、美術館は展示作品の撤去するかわりに、その作品の展示が倫理的にいかなるものであろうかっていうことを、出版部門を創設して継続して話を続けると。作品は実際に展示しなかったけれども、誌面上で言論として広く一般に議論を交わしていく展開が続いていくと聞いています。その議論を積み重ねていくような対応をしているようです。
藤田:よく日本で今は議論になっていることですが、芸術が社会に悪影響を与えるかもしれないときに、何がその芸術を正当化するのかっていう価値観の根拠をどこから調達できるのか。ジミェフスキの場合だと、どういうことの正当性の根拠に使っているのでしょうか。
丹羽:僕は本人じゃないんで代弁できないんだけれども、知っていて感じるところだけで言うと、彼はポーランドの作家であり、ポーランドというと歴史的にドイツから占領を受けたりとかしたところで、彼自身からは自分の国の歴史背景にあったユダヤ人問題だとかというものを別の視点から考えるためには、ある種のショックがなきゃいけないだろうというところで、やっているんじゃないかなとは思う。丸山さんは答えられますか?
丸山:丹羽さんが言うように、ヨーロッパの場合は言論の力が強いというか、悪影響を与えるかもしれないという問題が起こったことやその議論そのものがアートを取り囲む言説の力として価値をもっているように思います。それはいわゆる美とかそういうものじゃなくて、世界をどう認識しているのか、あるいはどう認識していくのかをアートとして出していくのが重要であり、そのために議論を生み出すこと、そしてそれを言説として語ることそのものが一つの価値として歴史的に存在していると思います。だから、そこにショックがあっても、それが一つの言説となりうる限りは、それを受け入れていく土壌があるんじゃないかと。
丹羽:難しいですね。ヒントになるかどうかはわからないんですけれども、ジミェフスキと僕はワークショップをやったことがあって、彼が言っていた言葉があります。彼はポーランド、ヨーロッパにいて作家活動をしていて、彼らの目線からすると、ヨーロッパでは現代美術が彼らがもっている伝統をうまく否定してきて、彼らはそれを力にすることができたけれども、日本は伝統によって現代美術の力が発揮することができないと。これはちょっとある種のヒントになるんじゃないかなと、今思う。彼らは否定したり破壊したりしていくことで、何か新しい価値を創造し、つくりだそうっていうものを信じているんじゃないかなと。そこにショックがあるのかもしれないけれど、否定して、更新していくっていうことに価値を見いだしているのではないだろうか。藤田さんいかがでしょう。
藤田:否定して更新することが、一般的に芸術家のやるべきことかもしれないけれど。挑戦するっていうことは、既成の今の状態に対して違和感がある、別の価値観なり美学なり世界認識を突きつけたいわけですよね。そして、それを更新したいわけじゃないですか。今の状態を破壊するわけだから、破壊した先に更新される世界がどういうビジョンになっているのか次第でよしあしが決まるんだと思うんですよ。
丹羽:ジミェフスキとのワークショップにビジョンがあるのかどうかっていうのは、僕には見えなかったですけれども。
藤田:日本とヨーロッパの比較みたいにいえば、日本もヨーロッパ型の公共性に変わればいいという意見もわかる一方で、日本固有の事情というかな、伝統的・歴史的・慣習的なものも無視してはいけないと思うんですよ。現実的に力をもっていますからね、それは。ポスト・コロニアリズム的な考えを採用するとしたら、単純に西洋の価値観でもって悪いと言ってしまうのもまずい気がする。ややこしいんですよ。でも、確かなのはヨーロッパ型の公共性をそのまま流用すればいいわけではないということ。
アツミ:藤田さんがさっき原始状態に戻れっていうことかなって言っていたけれど、ある一面ではそうかもしれないと思えてきました。アートが原始状態に戻るんではなくて、芸術祭の観客、あるいはアーティストやキュレーターも原始状態というか、アンラーニングの状態に戻るということはあると思います。日本、あるいはアジアの主客が未分化な伝達の様式とヨーロッパの主客が分化した二元論に基づいたコミュニケーションの様式は違うというステレオタイプな分類はたしかに可能なのですが、同時代のコンテンポラリー・アートはその両者を一つのイメージのなかで表象しているし、観客をそのイメージのなかに召喚することもできます。そこでは、観客がそれまでに学習してきた規範や価値観にショックを与えて、そこからゼロベースで何が問題になってるのかということを考え、対話することもできるでしょう。そして、そのハプニングのなかで、アートの作品になろうとしているもののイメージであったり、コミュニケーションのスタイルをそれなりにつくりかえこともできるのではないでしょうか。そして、そのことが美学や美術史、さらには人文学や社会科学の視点からの評価を経て、現在のイメージの価値や意義が文物となり、歴史をつくっていくっていうことになるのではないかと思います。
だから、ポーランドの建築家・デザイナー・彫刻家のオスカル・ハンセンの提唱した「開かれた形式」の影響を受けたアルトハメルとジミェフスキが提示しようとしているのは、同時代のなかで変容しつつあるイメージや歴史を動態的なものとして見直すという現状に対する挑戦的なビジョンなのではないかと思います。そこにはホロコーストへの反省も背景としてはあるはず。このようなビジョンを共有できるかどうかもまた、一つのアートをめぐるコミュニケーション形式のなかに自己準拠的に組み込まれているのでしょうけれど。作品のビジョンということで言うと、おそらくどのように意見を交わしたとしても、アーティストとキュレーター、さらには行政担当者の間で意見が完全に一致することはないように思います。アーティストの言葉には詩的言語のような側面も含まれているため、キュレーターや行政担当者はどこまでその言葉を公共に対して説明可能かということについては十分に検討する余地があるでしょう。
そのように考えると、どのくらい当事者間の対話を熟成させて作品という形態へと結晶化させていくことができるのかというところに、作品やそれを展示する展覧会や芸術祭の水準や正当性について考える根拠を求めることもできそうです。その意味では、芸術祭や展覧会には異質な人たちが集まって、アートのよくわからないビジョンについて話し合って、それぞれのディスコミュニケーション、失敗や傷を分有しながら、相手の身になって考えていけるという効果もあるだろうと思います。そのような行動や認識の変容を観客に迫る演劇空間の創出というのが、芸術祭や展覧会がアートを起点としたワークショップを行うことの意義ではないでしょうか。その後は、ポスト・プロダクション、あるいはポスト・エキシビションというところで、クリティックやレビュワーが事後的に評価することになります。そして、最終的には、作品と展示のプロセスのすべてがドキュメントのなかでイメージやテクストとなり、大文字のアート・ヒストリーに接続されるというのが一つの理念モデルとして考えられるのではないか。
丹羽:今話を聞いて思っていたのは、アーティスト側の意見として、そもそも芸術祭なんていらないんじゃないかって僕はときどき思うことがあるんです。もちろん制作したものを発表する機会があるっていうのは、アーティストにとっては誰しもがうれしいことだと思う。その反面、あそこに行かなきゃいけない、今度は行けないみたいに、旅芸人みたいに飛んでいってやらなきゃいけないっていうのも、反面喜ばしいことでもないなというのはときどきふと思う瞬間があるんです。それは藤田さんが最初に言ったような「地域アート」みたいな、その地域のことをなんて言うか、ほめたたえるような活動を見ているからこそなのかもしれないけれども。例えば、そもそもその地域に僕らが入っていかなくても、もうそこにきちんとしたコミュニティがあって、その地域で回っているんだから芸術祭なんかやらなくてもいいのかもしれない。例えば、お金のためにやらなきゃいけないっていう資本主義の要請からやっているものだったら一応の理由があると思う。でも、そもそも芸術祭なんてやらなくてもいいんじゃないかっていうことに頭が働くことがあるんです。その辺をどう考えますか。
藤田:やらなくていい芸術祭もありますね。でも、「なくていいものでもある」っていうのがアートの本質的な部分でもあると思うんですよね。しかし、芸術祭を意識的に擁護するとすると、芸術祭は何のためにあるとか、芸術は社会の役に立つべきなのかとか、何かを擁護するためにはその根拠になる価値観が必要なわけですよね。芸術祭っていろんな方がかかわっているのでぐちゃっとなっているから、何を根拠に、何をどう主張するかっていうロジックみたいなところで、自分の価値判断や趣味判断の根拠みたいなところに遡って考えさせられる機会が当然に増えてるんだと思うんですよ。僕はそこはけっこう重要なところだと思っていて、芸術際のなかでファンダメンタルな価値というか、何を価値の基盤に置くかみたいなところ、自分の考え方や価値判断の一番根っこにあるのは何かみたいなところに遡って考える機会が必然的に増えているのが、芸術祭の意義の一つかもしれないなと思っていて。
丹羽さんが霊とか霊性、お化けとか宗教とかにかかわっているのは、たぶんね、日本において価値観の一番基礎になっているのは、世間を大事にするとか、ご飯に箸をささないとか、無意識化した宗教観みたいなところが価値判断や趣味判断や規則に影響しているなかで、そこを知ろうとしているようにも見える。かなり懐疑的な態度で、だけれど。すると、必然的にファンダメンタルなところを考えさせられる。その次元から「公共性」の感覚をいじろうとしようとしているなと、丹羽さんの直島の作品を見て思ったんですよね。
公共性なり芸術のことを考えることが、結果として経済とか社会とか、政治とかよりも、もっと基底的で基礎的な価値みたいなところまで、大勢が遡って考えさせられる。無意識だったものが意識化されるっていうのは重要で、そのことで社会は変わるんですよ。公共っていっても、日本では公共って聞いても水道とかNHKとか役所のこととかしか思い浮かばないけど、日本では寺とか神社とかそれに相当するものだったはずだから、そこまで遡ってもう一回考え直して、もう一回つくり変えたりする試みをしているところが、公共性という観点から見たときに今の「地域アート」の面白いところかなと思う。
丹羽:なるほど、どうですか。
アツミ:芸術祭もアート作品と同じように、クオリティについて考える必要があるのですが、その評価基準のようなものをさらに考えていく状況に来ているのかなと思います。そこには観客動員数などの定量的な評価だけではなく、美術史や教育の観点から定性的な評価が求められるのはたしか。そして、その定性的な評価をめぐる議論にはアーティストやキュレーターだけでなく、クリティックや人文学や科学者などの有識者もより積極的に参加できる余地はあると思う。ただ、ドクメンタ14であったり、丹羽さんの作品を見ていたりして思うのは、政治や歴史の問題にどのくらい哲学カフェのようなコミュニケーションの態度で向き合うことができるのか、あるいは自らがマイノリティになるというか、あるいはマイナーな視点から対話するという意味では「マイノリティ設定の哲学カフェ」というものをどのくらい共有できるかというところは、芸術祭のクオリティの一つとして考えてもよいのではないかと思いました。
ただ、もっとシンプルに言うと、やっぱり芸術祭はあったほうがいいと思うんですよ。きれいで楽しいアートっていうのも、一つのファンタジーやセラピーの効果があるだろうし。何らかの浄化というものにも、観客に認識の変容を促す効果があると思います。その意味で、ぼくは芸術祭はもっと広がったらいいかなって。もし今の芸術祭が不要であるというのであれば、むしろ必要な芸術祭について議論して現状の芸術祭の不十分な面を調整して、来たるべき芸術祭に向けてバージョンアップしていけばいいと思うんです。だから楽観的に見て、ぼくは完全に芸術祭擁護論者です。
丹羽:丸山さん、いかがですか。キュレーターの立場として、芸術祭とどうかかわるか。
丸山:芸術祭だけでなくアーティスト・イン・レジデンスとかも含めてアーティストが移動して作品を制作するっていうのは一般的になっているし、そういった制度的な枠組みが用意されて、ある場所にいって制作するということが標準的なものとして考えられている状況というものを踏まえて、芸術祭を考える必要があると個人的には思っています。その制作を見守る地域の人たちと、片や移動し続けるアーティストの違いみたいなものが芸術祭では鮮明に見えてくると思っていて、藤田さんが故郷喪失者についておっしゃっていますが、地域性ということだけでなく、動き続けるアーティストという同時代性と、グローバリゼーションが国際的な芸術祭を可能にしている一方で、反グローバリゼーションが移動を困難にしているという状況も含めて、芸術祭を見ないといけないと思っています。
藤田:うん、わかります。
丸山:国際的に見ても「移動」できる人とできない人の差が大きく開いているので、芸術祭にグローバリゼーションの皮肉を感じるというか。
丹羽:なるほど。
藤田:一般論として、グローバリズムで根なし草的な考え方になった人たちほど、根源とか故郷とか民族とか、そういうような自分の根っこを仮想的に与えてくれるっていうものに熱狂しやすいっていうのはありますよね。「故郷喪失者」という言葉をあえて使っているのは、1930年代の日本の文芸の文脈でそういう言葉がはやったんですよ。故郷を失った感覚が広まって、その後にウルトラナショナリズムが蔓延した。根を与えてくれる幻想ですからね。たぶん、こういう根なし草的になっている人がイスラム国に入ってみたり、ファンダメンタリズムにはまってみたり、根源的なものに飛びつくんだと思う。
ドクメンタもそういうにおいを感じているからこそ、ああいうユダヤ人問題とか、ナチスの問題とか、政治的な問題や、移民の問題を意識的にやっているんじゃないかと僕は思うんですけれども。
だから、グローバリズムの問題と根っこというか、故郷とか地域の問題については、極めて難しいけれども、単純に飛びついてしまえる安易な幻想とは違う回路を丁寧に開くことではできるかなと思うんですよ。アートにはそれができるかなと期待してもいいのでは。
丹羽:なるほどね。アーティストの視点から言うと、勝手にやっているアーティストの活動を芸術祭だとか言って知らないところに呼ばれて行く違和感っていうのはすごい大きい。直島もそうだし、どこどこに呼ばれてそこで作品につくるということになりましたっていうときに一瞬感じる別のロジックに組み直されるおかしな感覚、さっき藤田さんが僕は関係ない文脈を無理やりつなげるみたいなことを言っていたんですけれど、僕云々よりも、芸術祭がそれをやっているじゃないかっていうのも感じます。今の時代、アーティストで生きるには、その要請に応じざるを得ない部分もあるんだけれども、それをしてでも芸術祭なんてやる必要あるのかなって、単純な疑問として僕はずっと考えていてる。今まで飛行機とかがなかった時代とか、どこまで各国の人を呼んで芸術祭を開催することは容易ではなかった時代が長かったわけだから、それと今っていうのはずいぶん状況が違っていて、今の問題は資本主義に引きずられ過ぎじゃないかなと思ったときに、そもそも芸術祭なんていらないんじゃないって、僕はときどき思うところがある。
藤田:たしかに芸術際自体がグローバリゼーションと交通の発展を前提とした、強引なコラージュみたいに見えなくもないですよね。
アツミ:資本主義の流動性を忌避するかたちで地域ごとの公共圏が保守反動的に伝統主義へと回帰するという傾向が強まるのであれば、芸術祭には国内外の公共圏のイメージを接続させて別の仕方でそれぞれの公共の閉塞的なイメージを変容させる効果も期待できるかもしれない。そして、そこから不和や敵対の関係が生まれ、「居心地の悪さ」のなかでさまざまな立場や視点から討議が形成されていくのかもしれません。
丹羽:今日の最初の最後のしめとしては、これから開催されている芸術祭に、僕らがどうかかわって構想していくかを考えたい。
例えば、藤田さんが今やっている震災文芸誌とかってありますよね。本を出版したりとか、文章を、僕も今日のトークのイベントのきっかけになった本を出しているんですけれども、言葉をつないでいる人に届けるっていう活動も片や必要だと思っていて。芸術祭のカタログとかガイドブックとかはあるんだけれども、それとはまた全然違うところで、批評の活動の力みたいなものもあるんじゃないかなと思っていて。ちょっとずれるけれども震災の文芸誌の先に何を見ていて、何を伝えようとしているのかなっていうことを藤田さんに、最後ちょっと聞ければなと。
藤田:僕、震災についての文芸誌をつくろうと思って動いています。東北の被災地の人たちの言葉を中心として集める本の企画をしているんですが、それは批評をなぜ書くかという問いともつながっています。つまり、紙に文字を並べて、それを印刷物として何千部か何万部かを配布して、図書館に保存してもらう行為っていうことになるんですが、概念にし、言語化し、対象化することを、印刷によって拡散するわけですから、一般化を志向するし、抽象化を志向する。そして空間的に広がりをもちますから、地球の裏でも読まれるかもしれない。時間的にも何百年ぐらいはどこかの図書館で残るかもしれない。それを意識することで、空間と時間において違うスケールを一瞬経由して事態を理解する視野が獲得できると思っているんですよ。芸術祭とか祭りとかはその瞬間瞬間が重要ですから、反省的思考になりにくいと思うんですよね。そこに批評っていうものをちょっとかませると、ちょっと違う見え方がしてくるかもしれないと僕は思っていて。言語や活字や出版のやれる役割もあると思うんですよ。
震災っていうのは、個別の体験で、瞬間瞬間を生きるので必死になるけれども、それである程度人に一般的に共有し、超長期的スパンのなかにそれを位置づけることによって、当人たちのなかに別種の反省的回路みたいなものをつくることによって、あるいは外部の人たちのその当人たちの個別具体的な経験を一般的なものとして共有することによって、ちょっとね、なんかこう断絶みたいなものが埋まりうるなと思っていて。だからね、出版公共圏みたいなものを僕はなんかけっこう信じているし、そこの力を使いたいと思っているんですよ。
丹羽:アツミさん、どうですか。今回、出版を引き受けてもらったわけですけど。
アツミ:丹羽さんは活動の初期段階から自分で本をつくったり、インタビューを公開していたりして、ある意味では自作自演の言論空間をつくっていますよね。活動の初期段階から共同体の不可能性について自分なりに批判的に検討するなかで本をつくっていたというところでは、藤田さんの文芸誌にもつながるような問題意識があるのではないかと思いました。政治、歴史、マイノリティを扱ったアートはどうしてもセンシティブな問題で人を傷つけるかもしれないけれど、人を傷つけないようにする配慮は前提としたうえで、どのように傷を分有できるのかというテーマについても対話型のワークショップのなかで考えていく必要があると思う。そこから、研究者の人たちはそれぞれのフィールドでマイナーな問題を発見すると思うんですよね。芸術祭に行って、ワークショップを体験して、いろいろな人と話して、何かを感じることで生まれる人文的なエッセイが、現在の歴史をつくっていく、さらには批評の概念をつくりかえていくのだと思います。批評による歴史の見直しという可能性に賭けていえば、芸術祭はたくさんの批評を集める必要があるといえるでしょう。
藤田さんの震災文芸誌の構想に引きつけて言うと、テリー・イーグルトンが『批評の機能』[9]のなかで「対抗公共圏」について語っていたことを思い出します。プロレタリアートやマイノリティの抑圧された利害や欲望が政治的な象徴形式となることで、公共圏における闘争の場、あるいは議論や対話の場ができるそうです。そういえば、近代国家において人間のよりどころとなるのが故郷であり家庭の暖炉だとも言っていましたね。ポスト・モダンを経たポスト・トゥルースの現在では、カウンターの同志たちが囲む暖炉の火が燃えさかって、家庭や故郷、さらには国家をも焼き尽くしてしまいそうだということなのかもしれません。それでは、炎上する討議的、あるいは敵対的な公共圏のなかで、人々はどのように対話や議論を醸成していけるのだろうか。震災文芸誌や出版公共圏のお話は、イーグルトンの英文学や批評、あるいは批評誌のバージョンアップとしても読めそうなので、楽しみなビジョンだなと思いました。
そこから、アートを政治的な象徴形式の表象として見ると、芸術祭を起点とした「アート文芸誌」という構想にもつながりそうですね。芸術祭はアーカイブやドキュメントを充実させられるように予算設計を見直して、批評家や人文社会科学をはじめとするさまざまな領域の専門家に依頼して批評的なエッセイを集めることで、その公共のビジョンをより多様性に開かれたものにできるはず。芸術祭と出版公共圏が重なり合ったところに、新しい公共的な知のあり方が見えてくるのではないかと思います。いまもし芸術祭というものが必要とされていないのであれば、批評や批評言語の機能不全と一体化しているとも言えると思うんです。だから、まずは芸術祭におけるアーカイブのあり方を議論し、ドキュメンテーションのプロセスを検討し、さまざまな批評文を集めたカタログをつくるところからはじめるとよいのではないでしょうか。
アツミ:そろそろ、時間なので・・・。
丹羽:どうぞ。
尾﨑:尾﨑全紀といいます。今日のトークイベントはいつものNADiff a/p/a/r/tのイベントとは違って、写真撮影やツイッターでのつぶやきが禁止ということで、かなりデリケートな話をする場に来ているのかな、と感じています。個人的には、堀之内出版の『地域アート』の冒頭で、星野太さんと対談されておられる藤田直哉さんのお話を直接うかがうことができるということと、西山雄二さんの映画『哲学への権利』[10]の朝日カルチャーセンター新宿校での上映会で知り合って以来の知人であり、普段は編集とかで裏に隠れているアツミさんが出演者として壇上に上がられるということで来ました。
NADiffのサイトでは、アーティスト・丹羽良徳さんの作品の一環としてつくられた批評集『資本主義が終わるまで』の刊行を記念したトークイベントということになっていますが、今日初めて、ここまで話を聞いていて、「え? もしかして、デリヘル呼んで、Twitterとかでむっちゃ炎上してた人って、この人だったの?」ってようやく気づいたんですけども(笑)。ただ、今日の話をずっとうかがっていて、明らかな事実誤認についてもまったく正されないままに、事実関係みたいなものがものすごく圧縮というか、まとめるというか、歪められたかたちで、いろんなところで批判されているのだ、ということがよくわかりました。
で、今日のトークイベントのタイトルである「芸術祭の公共圏―敵対と居心地の悪さは超えられるか?」のことも考えると、要するに、今日は、実は、あの有名ないわゆる「デリヘルアート事件」について、フィルムアート社から『社会の芸術/芸術という社会』が刊行され、その後の諸々の波紋や経緯を含めて、単に丹羽さんを擁護するとかいうのとは違う次元でいろんなことをきちんと考えましょう、という場だったんじゃなんじゃないかと認識を改めている次第です。
『社会の芸術/芸術という社会』では、詳細な事実関係の確認や当事者への聞き取りもなしに丹羽さんが批判されているというお話だったのですが、編者の顔触れなどから私が勝手に憶測すると、どうせまた、「人権」というマジックワードを使って、かなり無理筋の話をしているのではと邪推してしまいます(苦笑)。が、まあ、読んでもいない本の悪口を言っても仕方ないので、とりあえず、そういう一般論は措いておきます。
アツミさんは、当日、事件の現場に居合わせておられて、この事件とその後の経緯も含めて、ずっとフォローしておられ、この件について、デリダの難しい言葉を使って書かれ、Amazon Kindleでも買えるという、難しい論文というか、文章があるというお話でした。今日のトークイベントの雰囲気から推測すると、たぶん、現場にいた人の単なるレポートという以上のかなり複雑で繊細で突っ込んだ内容のものだと思います。こちらはまだ読んでないので、買って読んでみようとは思っていますが、読んでも理解できる自信がないので(笑)、あらためてタイトルと、あとどういう内容なのかということをざっくりでいいので教えていただけるとありがたいです。
アツミ:ご質問、ありがとうございます。タイトルは「フレーミングするパレルゴンのパルマコン―丹羽良徳の〈88の提案〉を後に」というものでした。本質的にアートには社会における価値観を見直させる機能があると思うのですが、ジャック・デリダが「プラトンのパルマケイアー」のなかで言っていたパルマコンっていう毒と薬の両義的な意味を内包する概念と「絵画における真理」のなかで言っていたパレルゴンという作品の外延、額縁、あるいはフレーム(枠)という概念に寄せて、「88の提案」について論じたものです。今日も話に出ていたように、ある作品を誰が、どのように見るかによって、その認識や評価は変わります。事前のコンセプトと事後の観客による受容の違いによって、アーティスト自身も展示物や作品への向き合い方が変わることもあると思います。そういった作品受容のダイナミズムについて、SNS上の炎上(フレーム)という問題ともつながってくる昨今のポスト・トゥルースの状況も踏まえて論じたものです。「88の提案」の展示や展示後の出来事を振り返りながら、パレルゴンと炎という2つのフレームのなかで毒あるいは薬の間を揺らぐアートの両義的な効果が浮き上がるような内容になっていれば。「88の提案」のような展示物を作品だという人もいれば、作品だといわない人もいるし、社会によい影響を与えると言う人もいれば、悪い影響しか与えないと言う人もいる。そういう人々の相反する意見のアゴニスティックな討議が作品やアートをめぐるコミュニケーションのコードを形成し、そしてアンタゴニスティックな敵対とともに価値転倒が起こり、コミュニケーションのコードが別の仕方で分出していく。「88の提案」という展示物はそういう倒錯的、あるいは壊乱的ともいえる円環構造をもつ解釈群を人々に提出することによってアートと非-アートの間で揺らぐ展示物、あるいは作品だったのではなかったかという解釈です。また、そういった解釈をめぐる再帰的なコミュニケーションが維持されることで、事後的には「88の提案」をアート作品にしてしまうともいえるでしょうか。ちなみに、丹羽さんは当日、「88の提案」を作品ではなく展示物だって言い張っていたのが印象に残っています。だから、丹羽さんは結局のところ、アルトハメルとジミェフスキとのワークショップを経験して、あらためて社会のなかのアートとは何かということを観客に、参加者に、あるいは学芸員に、そして自分自身にも問いかけていたのではないかとも解釈できるかもしれません。そこに見られた態度は、感覚的な面白さというよりも、実存的な無私とでもいえるものではなかったかと思います。そして、いつもアイロニカルな態度ではあれ、人々に問いかけ、対話的であることをやめようとはしませんでした。
アツミ:ところで、これからの予定は?
丹羽:少し先にはなるけれど、2018年の秋、1968年から毎年開催されているオーストリアのグラーツの芸術祭「steirischer herbst(シュタイヤーマルクの秋)」で新作コミッションを予定してます。前年までは、アヴァンギャルドな舞台芸術が中心だったのですが、2018年から企画体制が刷新されてより現代美術を中心にする方向になりました。今回は「Volksfronten(国民戦線)」というテーマがつけられていて、世界的にみて各国が右傾化しつつある現状やグラーツがかつて親ナチス運動で有名だった過去などに、どのように芸術から応答するかということを問うストレートな芸術祭になると思います。僕の新作は、一般公開することが禁止されているナチスにかかわる遺物を扱うプロジェクトで、会期中グラーツに滞在してワーク・イン・プログレスとして順次公開していく予定です。
2019年はいまのところオーストリアと日本での展覧会を合計で4件予定してます。それぞれ異なる方向性の作品を予定していますが、日本では2020年の東京オリンピックのフェイクドキュメンタリーの作品もその一つとして予定してます。まだしばらくはウィーンを拠点としつつ、さまざまな都市の人々と協働していくつもりです。
アツミ:参加型でワーク・イン・プログレスの作品となると、歴史そのものをつくっているような印象さえ受けますね。いずれにしても、丹羽さんのアートでは友が敵になったり、敵が友になったりと、デリダが『友愛のポリティックス』[11]で遠隔的な距離の詩学をめぐって書いていたテレイオポイエーシスという言葉も思い出させてくれます。丹羽さんの作品のなかから呼びかけられる声は、誰に、どのように届くのだろう。そして、そこから立ち上がる公共システムはいつ、どのような姿をとるのだろう。AIについての作品も構想しているということで、これからの展開も楽しみにしています。今日はありがとうございました。
丹羽:今日はどうもありがとうございました。ではまた、ウィーンで。
〈註釈〉
[1]Claire Voon.LGBTQ Refugee Rights Group Steals Artwork from Documenta in Athens.2017.
https://hyperallergic.com/382407/lgbtq-refugee-rights-group-steals-artwork-from-documenta-in-athens/
[2]クレア・ビショップ.敵対と関係性の美学.星野太訳.表象05.月曜社,2011.
[3]エルネスト・ラクラウ,シャンタル・ムフ.ポスト・マルクス主義と政治 根源的民主主義のために.山崎カヲル、石澤武訳.大村書店,1992.
[4]北田暁大,ほか(編).社会の芸術/芸術という社会 社会とアートの関係、その再創造に向けて.フィルムアート社,2016.
[5]F.アツミ.フレーミングするパレルゴンのパルマコン―丹羽良徳の〈88の提案〉を後に.Art-Phil.2017.
https://art-phil.hatenablog.com/entry/20171103/1509707585
[6]遠藤水城,ほか.「表現と倫理の間で」.HAPS.2016.
http://haps-kyoto.com/haps-press/bye/bubu_yamada_interview/
[7]佐久間卓也・阿部秀俊.「デリヘルを呼ぶ」は芸術か.憲法考 第一部 萎縮する表現④ 「自由」の責任.京都新聞.2016年5月4日,8面.
[8]田中辰雄,山口 真一.ネット炎上の研究.勁草書房,2016
[9]テリー・イーグルトン.批評の機能:ポストモダンの地平.大橋洋一訳.紀伊國屋書店.1988.
[10]西山雄二.哲学への権利.勁草書房,2011.
[11]ジャック・デリダ.友愛のポリティックス I.鵜飼 哲訳,大西雅一郎訳.みすず書房.2003.
ドキュメント全編は有料コンテンツとして公開中→

〈全編版:目次〉
1.芸術祭における「居心地の悪さ」と介入の倫理の問題系に向かって
2.地政学的な歴史観と展覧会のストラテジーに対する異議申し立て
3.アートに消費される「マイノリティ」と疑問に付される討議空間の公共性
4.日本の公共性の問題点が凝縮している炎上とヨーロッパにおけるアートと言論の力
5.芸術祭なんていらない? グローバリズムのなかで芸術祭に抱く違和感
6.芸術祭はなくなってしまってもいい? 展覧会は本当に必要なのか?
7.「88の提案」をめぐるデリケートな話と芸術祭のこれからについて
8.東京オリンピックに向けて新国立競技場の周縁を彷徨う前に
9.特別寄稿:「新国立競技場の周縁を彷徨う レポート」―藤田直哉
10.特別寄稿:「オリンピック聖火は何のために燃えているか?」―丹羽良徳
●PROFILE
丹羽良徳 Yoshinori Niwa
1982年生まれ。ウィーン在住。タイトルに示される行為や企てを路上などの公共空間で試み、既存の価値観を解体し、現実とのギャップを露呈させる、交渉の失敗を繰り返す出来事の一部始終をビデオ記録として制作する。主な展覧会に「瀬戸内国際芸術祭2016」(2016年、直島)、「愛すべき世界」(2015年、丸亀)、「あの言語は言語みたいに聞こえる」(2017年、ロンドン)、「ダブル・ヴィジョン―日本現代美術展」(2012-3年、モスクワ、ハイファ)、「あいちトリエンナーレ2013」(2013年、名古屋)、「六本木クロッシング2013」(2013年、東京)、ほか。
藤田直哉 Naoya Fujita
1983年札幌生まれ。批評家。二松学舎大学、和光大学非常勤講師。東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。専門は筒井康隆と戦後日本SF。評論は、SFから、サブカルチャー、映画、美術、純文学などさまざまな領域に跨っているが、「同時代・芸術・人間」の三項が基本主題。編著『地域アート 美学/制度/日本』(堀之内出版、2016年)で話題になり、日本における「地域アート」(地方における芸術祭)に対する、評論を展開している。その他の著作に、『虚構内存在』(作品社、2013年)、笠井潔との対談『文化亡国論』(響文社、2015年)、共著に『floating view 郊外から生まれるアート』(トポフィル、2011年)などがある。
丸山美佳 Mika Maruyama
長野県生まれ。横浜国立大学大学院建築都市文化専攻修士課程修了。ウィーン・東京を拠点に、アートプロジェクトに携わりながら、展覧会やパフォーマンスの批評、レビューを寄稿している。主な論考に、「社会をとりまく『到着』が意味することは何か?」(美術手帖11月号、2016年)、「『踊れ、入国したければ!』上演にあたって」(KYOTO EXPERIMENT ブックレット、2016年)など。現在、ウィーン美術アカデミー博士課程にて現代美術における身体の関係性について研究中。キュレーターとして巡回展覧会「Behind the Terrain」を東南アジアにて進行中(2016年~)。
F.アツミ F. Atsumi
編集・批評、Art-Phil。“アート発のカルチャー誌”としてブックレット「Repli(ルプリ)」の発行を中心に活動。これまでの出版物に、『デリケート・モンスター』(Repli Vol.01)、『colors 桜色/緑光浴』(Repli Vol.02)、『歴史上歴史的に歴史的な共産主義の歴史』、『OrNamenTTokYo』、などがある。また、批評的な視点に基づいた理論的な実験として、「サーカス・ノマド」の企画のもと、展示やイベントなどのキュレーションに時として携わり、「春の色」(2013年)、「十字縛り キャッチ・アンド・リリース」(2013年)、「テロ現場を歩く」(2014年)などに取り組んできた。アート、哲学、社会の視点から、多様なコミュニケーション一般のあり方を探求している。
●お問い合わせ

NADiff a/p/a/r/t
150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F
TEL. 03-3446-4977